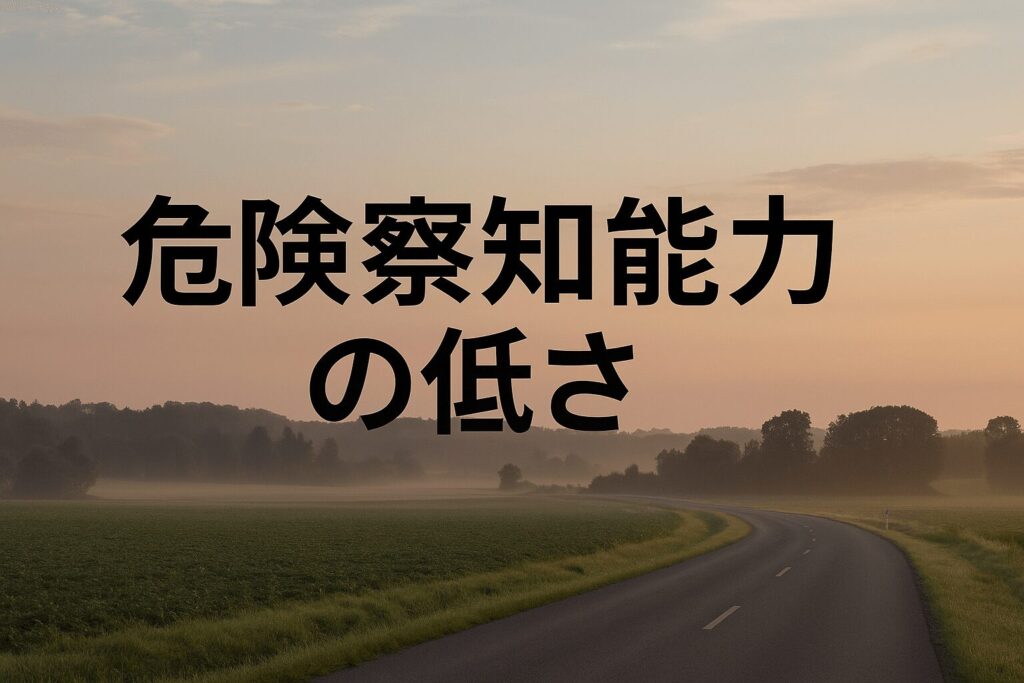
私は人生を通して、失敗して学ぶことが多すぎると感じています。
いつも新しいことに挑戦したり、未知の事に遭遇すると、大抵失敗してしまいます。
ただの失敗ならいいのですが、悲惨な状況になったり、取り返しつのかないことになる事も多々ありました。
何故、毎回何かしら経験のないことをすると、まず辛い思いをして学んでから、「次は失敗しないように気を付けよう」となってしまうのでしょうか。
昨日の事です。
いつもの1回目の食事の後に薬を飲むのを忘れました。
仕方が無いので、2食目の後に飲みました。
ちなみに私は1日2食です。
薬は毎回、400mlくらいの湯冷ましを作っておいて、それで薬を飲んでいます。
そして今回、何故かその400mlのぬるま湯を勢いよく一気に飲んでしまったのです。
普段だったら100mlくらいをゆっくり薬と一緒に飲みます。
しかし何を思ったのか、がぶ飲みをしてしまいました・・・。
頭の中では、「薬を飲み忘れたので一気飲みしなければ」という謎の必死感があったのかもしれないです。
そしてその結果、腹痛に襲われました。
普段しない、食後すぐに薬と一緒に400mlの水の一気飲み。
また、意図せず新しい事に自然と挑戦してしまい、2~3時間胃の当たりが膨らんでしまい、腹痛に耐えていました。
実はこの水の一気飲みをする前に、ワンテンポくらい葛藤があったと思います。
1~2秒くらい「本当にしていいのだろうか」という疑問を一瞬感じていました。
しかし、それもほんのわずかで、躊躇なく水の一気飲みを行ってしまいました。
腹痛に耐えながら、この状況を調べてみると、食後に水をたくさん飲みすぎると胃の消化が悪くなり、腹部膨満感が出て消化吸収が上手くいかないとのことでした。
今回、この経験を失敗して学んだので、忘れない限り今後、「食後の水の一気飲み」には気を付けようと頭の片隅に刻んでいます。
しかし、このように痛い目にあってから「次回気を付けよう」など、人生で散々体験してきました。
どう考えても普通の人よりも知らない・新しいことをすると、大抵酷い状態になるのは何故だろうと、よく疑問に思っていました。
そして「この失敗して学ぶ」問題が多い理由は、「ASDと直接関係があるのではないか」とも思っています。
普通の人が持ち得ている脳のストッパーや何かが制御しない・働きづらく、思考停止状態になっているのではないかと。
結果、危機管理が疎かになっているのかもしれないです。
過去の失敗で学んだ出来事について
沢山あったと思うのですが、はっきり覚えているものは少なく、印象に残っている出来事だけ書いてみようと思います。
まず真っ先に思い出されるのが、強引に連れ回された出来事です。
プロフィールにも少し触れたことがありますが、当時の私にとっては非常に衝撃的な経験(事件)でした。
19歳くらいの時、洋服を買いに自転車で出かけたときのことです。
途中で軽トラックに乗っている若い男性2人に声をかけられました。
見た目が怖い感じだったのですが、道を尋ねてきただけだと思い、信用してしまいました。
そのとき、後ろのナンバープレートが半分に折れており、不審に感じる部分もありました。
しかし、ASDの「疑いづらさ」「危険に気づきにくい傾向」もあり、その場の状況や問題を理解できていませんでした。
このような経験は初めてで、ASD特有の“未知の出来事で思考が固まってしまう”状態も重なり、流れに身を任せてしまうような形になりました。
気づけば自転車を荷台に載せられ、私自身も助手席に乗せられました。
その後、相手の様子が急に不穏になり、信号無視をしたり危険な運転を始めたりしました。
私は、極度の緊張と恐怖の中で思考が止まり、パニック状態になりました。
さらに、助手席から外に出られないように車を壁際に止められ、脅迫させられて所持金(5千円と小銭)を盗まれました。
その時にポイントカードも取られ、そこには私の住所や電話番号が記載されていました。
ようやく解放されて一旦は落ち着いたのですが、その後、約2年以上にわたり、家には脅迫めいた電話が続いていたそうです。
当時私は大学で一人暮らしをしていたため、親が心配して伝えなかったそうです。
数年後に警察へ相談したところ、「なんでもっと早く言いに来なかった」と言われてしまいました。
この経験は、今でも未知の出来事で困難な状況に陥ると、強く思い出されます。
もう1つ、6〜7年ほど前のことです。
久々に外出して心療内科へ行った帰りに起こった出来事がありました。
運悪く雨が降ったりやんだりしており、駅からの帰り道で傘をさすかどうか迷っていました。
結局、濡れてもいいと思い傘をささずに歩くことにしたのですが、駅から無料の自転車置き場までは10分ほど歩く必要があり、左手に畳んだ傘、右手に荷物を持ったまま、少し小走りになりました。
そして不注意からか、道の段差につまずいてしまい、両手がふさがっていたために受け身が取れず、そのまま前のめりに倒れてしまいました。
右手の3本くらい指を深く傷つけてしまい、白い骨が見えるくらいえぐれてしまいました。
痛みと出血もありましたが、周囲の人に見られて恥ずかしくなり、その場をすぐに離れてしまいました。
病院へ行きましたが、治るまでに1か月ほどかかり、その間ずっと痛みが続きました。
今でも指先には当時の傷跡が残っており、皮膚が盛り上がったままになっています。
この経験から、「両手がふさがっているときに走るのは危険」ということと、「急がば回れ」という教訓を今でも強く心に根付いています。
ASDと失敗して学ぶについて
「失敗は成功のもと」と言われていますが、私の場合は失敗したら何倍もの大変な事態に陥ったり、取り返しのつかないことになる事がよくありました。
そしてその新しい・知らない出来事に遭遇して運よく上手くいくことはほとんどありません。
普通の人の何倍も失敗して酷い目に合うことが良くあるので、本当に恐れています。
そしてこれは、ASDと相関関係があると思っているのです。
初めて就職した時に、出向という形でいきなり別の会社へ移されました。
その時に、その会社の新人の人と帰りのバス停あたりで初めて会話をしたときの事です。
私は何を思ったのか、いきなり自分の就職した会社の給料の話をしだしたのです。
何の脈絡もなく。
そして案の定、相手は引いていました。
私の脳内ではたぶん、初めての人との接触でどうしたらいいのかわからない→なんか急に頭の中で就職氷河期での低すぎる給料が頭をよぎった→そしてそのまま意味不明でその場にそぐわないことを語ってしまった。
結局、その話が出向した会社で広まったようで、ヤバイ奴扱いされ、たった1日で避けられるようになってしまったのです。
ASDの特性からくるコミュニケーションや社会性の問題によって引き起こされた、致命的な失敗。
そして、この出来事から私は「とにかく自分の思ったことをいきなりしゃべらない」ということを学んだのです。
特に初めての事に対する脳のフリーズというか働きが悪すぎるので、本当に気を付けなければならないです。
でも気を付けていても、その場面に遭遇すると考えが及ばず、マルチタスクの出来なさから1つの事しか頭にない状態となってしまいます。
普通の人でもいちいち、自分の問題を心に感じ続けながら気を付ける、というのは難しいと思います。
いや、無意識化や自然にできているようです。
しかし、ASDにはそれが難しすぎる。
失敗から経験して教訓としても、できることとできないこと、頭に強く印象付けていないと難しい。
そして未知の出来事や新しいことに対しては、よりそれが強くなってしまいます。
ASDが失敗から学ぶことが苦手?
結論から言うと、ASDの特性は失敗しやすいというだけではなく、
「失敗を避けるための直感が働きにくい」
「危険を予測するブレーキが遅れてしまう」
という形で影響することが多いようです。
ASDの人は、新しい状況や予定外の出来事に直面したとき、脳の切り替えが一瞬遅れてしまうことがあります。
普通の人ならほんの一瞬で感じ取れるはずの「これは危ない」という微妙な感知を、その場ではうまく認知できないのです。
さらに、頭では「気をつけないといけない」と理解していても、実際の行動に反映されるまでにタイムラグがあり、結果的に「分かっているのに止められない」状態になってしまうこともあります。
これはIQの差によって違ってくるとは思います。
また、ASD特有の記憶の強さも影響します。
過去の失敗体験によって、「また同じことが起きたらどうしよう」というような不安が大きくなりやすいのですが、その場で危険を回避する直感的な学習(経験)がうまく機能しにくいのです。
普通の人が「次は気をつけよう」で済ませられるところが、ASDの場合は「次同じ状況になったらまた大きなダメージを受けるかもしれない」という恐怖として刻まれてしまう。
そのわりには同じ失敗を未然に察知してブレーキをかける仕組みが弱いという、かなりつらい問題がるのです。
この認知のタイムラグ”と記憶の強烈さ”の組み合わせが、ASDの人にとって「失敗から学ぶ」を他の人以上に難しいものにしているのだと思います。
まとめ
私が人生でずっと感じていた、とにかく大失敗して辛い経験をしてから学ぶということ。
取り返しの利く失敗であれば良いのですが、何故か大失敗してしまう。
ASDの特性も関係しているのだろうけど、運の悪さもあると思っています。
どちらにしても、ASDの人にとって、初めての事は十分に気をつけても気を付けすぎることは無いということ。
でも、経験していないと注意すること自体が難しい。
人生は予想できないし、ASDの選択ミスからくる物事のミスも大きすぎます。
なのでいつも言っていることですが、ASDの人には周囲の理解やサポートが必須なのです。
それが無いと、私のように真性ひきこもりになったり、メンタルに問題を抱えてしまう未来が待ってます。
この問題は、ASDだけでなくADHDやLDなど他の発達障害や、IQの低い人にとって人生の 「試練」 だと思います。
この課題こそが、発達障害の生活上の重大な困難として、国の福祉制度や法律が定める支援条件に正式に含められるべき項目だと強く感じています。
FAQ(よくある質問)
Q. なぜこの記事を書こうと思ったのですか?
A. 自分自身が人生の中で何度も大きな失敗をしてきて、そのたびに「これはASDの特性が影響しているのでは?」と思うことが多かったからです。同じように悩んでいる人に、少しでも共感やヒントになればと思い書きました。
Q. ASDの人は本当に失敗しやすいのでしょうか?
A. 私自身の経験からすると、未知の出来事に直面したときの“認知のタイムラグ”や“危険予測の弱さ”は明確にあります。もちろん人によりますが、特性として失敗につながりやすい場面が多いのは事実だと思っています。
Q. どうすれば失敗を減らせますか?
A. 正直に言うと「完璧には減らせない」と思っています。ただ、事前にチェックリストを作ったり、同じパターンを生活に組み込んだりすると、かなり軽減されます。周囲の理解やサポートも大きな助けになります。
Q. この記事に書かれているような失敗を経験すると、どうしても落ち込んでしまいます。どう向き合っていますか?
A. 私も落ち込みますし、かなり引きずることもあります。ただ、「特性だから仕方ない部分もある」と一度区切りをつけて、次に同じ状況が来たときにどうするかだけを考えるようにしています。
Q. ASDの失敗体験を書くことに意味はありますか?
A. あると思います。自分の頭の整理にもなるし、同じ悩みを持つ人が「自分だけではなかった」とホッとできるかもしれません。理解してくれる人が増えるきっかけにもなります。
