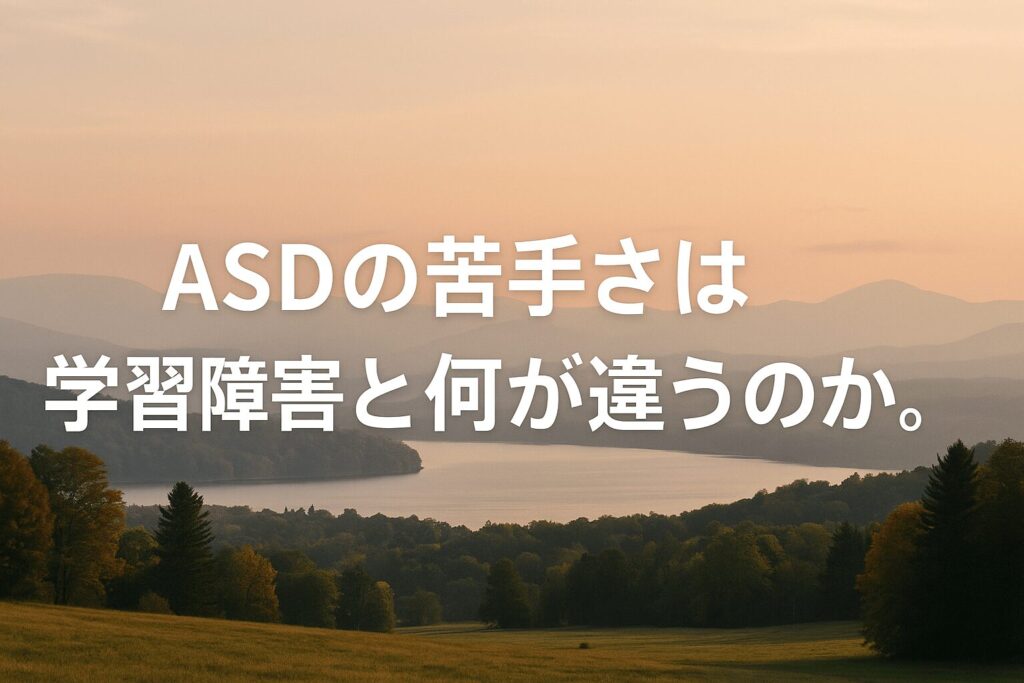
発達障害のASDと、学習症(学習障害)について気になる事があります。
それは、ASDの特定の出来なさがどうして学習症に分類されないのか、ということです。
ASDの自分自身の問題について考えたのですが、昔から頭の中で情報を処理したり、概念を把握したりすることが凄く苦手です。
この想像や空間把握が苦手すぎる問題は、いくら努力しても成長がほぼ出来ないです。
先天性であり、人生の最後まで続きます。
学習症も同様に、ある特定の学習が困難であったり、どうしても習得しづらい領域があります。
このASDのある特定の出来なさと、学習症の出来なさは何故分けられているのでしょうか。
ちなみに私の想像や空間把握が苦手、もしくはほとんどできないという問題は、今でもずっと抱えています。
頭の中で形や構造をイメージしたり、見えないものの位置関係を思い浮かべるといった作業が、どうしてもできないのです。
そしてその特性は、学生時代の勉強や学習にも大きく影響していました。
たとえば1998年、大学でC言語の授業を受けていた頃のこと。
私はどうしても「配列」や「ポインタ」の概念が理解できませんでした。
それ以外の文法(if文やfor文など)の初級くらいは少し理解できたけど、配列になると頭の中で構造?を考えながら処理をイメージすることができなかった。
ポインタも、メモリ上の動きを想像して操作するということが理解することが全くできなかったのです。
今思うと、ASDの想像力の欠如が、脳の理解に問題が発生していたからだとわかりました。
目に見えない対象の位置情報を想像したり、抽象的な構造を頭の中で操作したりすることが、どうしてもできない。
苦手というか、不可能。脳の情報処理の回路自体がその動きをしてくれない。
そしてこれは、学習症の特徴と非常によく似ているのではないかと思ったのです。
ASDの抽象構造の理解困難が学習症(特に算数障害や非言語性LD)の問題と酷似しているのではないかと。
ASDの想像力の困難や柔軟な視点切り替えの苦手さは、学習症の1つと考えてもいいと思うのです。
実際、頭の中で想像して学習(理解)することが困難になっていたのだから。
でも1つ疑問に思うことがあります。
世間では良く、発達障害のASDは、プログラミングに適性があると言われていることです。
確かに、プログラミングは型がきっちり決まっているし、ルールがはっきりしています。
なので一度法則や定義を理解してしまえば、特定の分野に強いこだわりや集中力があるASDであれば合っている仕事だとは思います。
では何故、私はプログラムが理解できず、不向きだったのか。
それは配列やポインタの時点でつまずいてしまって先にすすめなかったからです。
でもASDの人でもプログラマーに向いている人もいる。
この矛盾の理由は、実はIQに差があると思っています。
例えば私の場合、全IQ67でした。
特に知覚統合62くらいで異常に低く、空間的な情報の把握や抽象構造のイメージ化を理解するのが非常に苦手です。
でも、ASDは別にIQの高低差で診断されてはいないということです。
全IQが110くらいの人が、たとえば知覚統合が80くらいでその他が110を超えている場合。
この場合、確かに私と同じように構造処理や空間的思考が難しいと思う。
でも、IQに凹凸はあってもベースの差が全く違うので、高IQの人は全く理解が及ばないというわけではないということです。
要するに普通の人よりは理解はしずらいけど、一度理解してしまえばプログラマーは適職になる可能性があるということなのです。
このIQの高低差による理解力の差が、学習症の定義に触れるのではないかということです。
高IQのASDの場合は、理解が及ぶ。しかし、低IQの場合は理解できない、もしくは非常に難しくなってしまう。
学習症では、「IQは平均以上にも関わらず、特定のスキルだけが極端に苦手になる」という特徴があります。
私の場合はその逆で、「IQ全体が低めで、さらに特定の能力が極端に苦手」という構成でした。
診断名としては学習症には該当しないのですが、実際の困難さは学習症と非常によく似ていると思ったのです。
もちろんASDだけでなくADHDにも、努力ではどうにもならない成長が期待できない特性はあります。
たとえば、ワーキングメモリが著しく弱い、注意がすぐに逸れてしまう、衝動性が抑えられないといった特性は、どれだけ訓練しても劇的に改善するものではないということです。
これも、学習症の「どれだけ努力しても特定領域が身につかない」という性質と共通しています。
しかも、学習症(LD)は、ASDやADHDと明確に診断が分かれています。
他の発達障害がなくても、単独で発症しているケースもあります。
では、どのような基準を持って違うとされているのでしょうか。
発達障害(ASD、ADHD)と学習症(LD)の分類の違い
DSM-5での学習症の定義は、知的能力は十分にあるにもかかわらず、読み・書き・計算など特定の学習領域に困難がある神経発達症です。
診断基準は、
- 読字障害(ディスレクシア)
- 書字表出障害(ディスグラフィア)
- 算数障害(ディスカリキュリア)
他の発達障害がなくても単独で存在し得るとのことです。
ASDとADHDの併存についても、LDのある子の20〜50%程度がADHDを併存、ASDの子の30〜60%に学習の偏りや学習障害がみられる、と言われています。
基本的にASDやADHDは、コミュニケーションの難しさ、注意散漫・多動・衝動性が問題となってます。
でもよく考えると、ASDやADHDの中にも、学習症のように「どうしても努力では身につきにくい」が存在しています。
ようするに、発達障害の中には、生まれつきの脳の情報処理によって、特定の学習がとても難しくなるケースが確かにあるわけです。
ただ、診断上はそれらをLDとは別で扱っています。
私の場合、想像力や空間把握の弱さのせいで、プログラミングだけではなくて、数学の図形や空間問題・地図の読解など、「構造を頭の中で組み立てるタイプの学習」が本当に苦手でした。
もちろん、IQの低さによる理解の難しさもあります。
でも、明らかにASD由来の「イメージ操作のしづらさ」や「抽象構造を頭の中で動かせない」などの問題によって理解が止まってしまう部分があって、これは学習症の特徴とかなり重なっていると思うのです。
ASDでもIQの高低差でこの問題がどれくらい困難なのかもまた変わってきます。
だから、「発達障害の症状は同じ人はいない」とされているのだと思いました。
まとめ
今回は、自分のASDの問題が何故LDに含まれないのかを考えてみました。
とりあえず、学習症の概念は
読字障害(ディスレクシア):読むのが極端に苦手。文字が踊って見えたり、音と文字の対応がうまくいかなかったりする。
書字表出障害(ディスグラフィア):書くのが苦手。字がすごく汚かったり、文の構成が混乱したり。
算数障害(ディスカリキュリア):数字や計算の概念がうまくつかめない。暗算が苦手とか、繰り上がり・繰り下がりでパニックとか。
これらはどれも、学習の特定分野におけるスキルの獲得困難が明確に現れるものとして定義されています。
私が抱えているような「想像力」や「空間把握」の困難**は、学習にも問題を起こすけど、それ以上に対人関係や社会の適応能力など、勉学以外にも大きな問題が起こります。
ようするに、人生の様々な場面で問題を引き起こすので、学習症の枠組みに収まらず、発達障害の代表的なASDとしてまとめられているのだと思いました。
