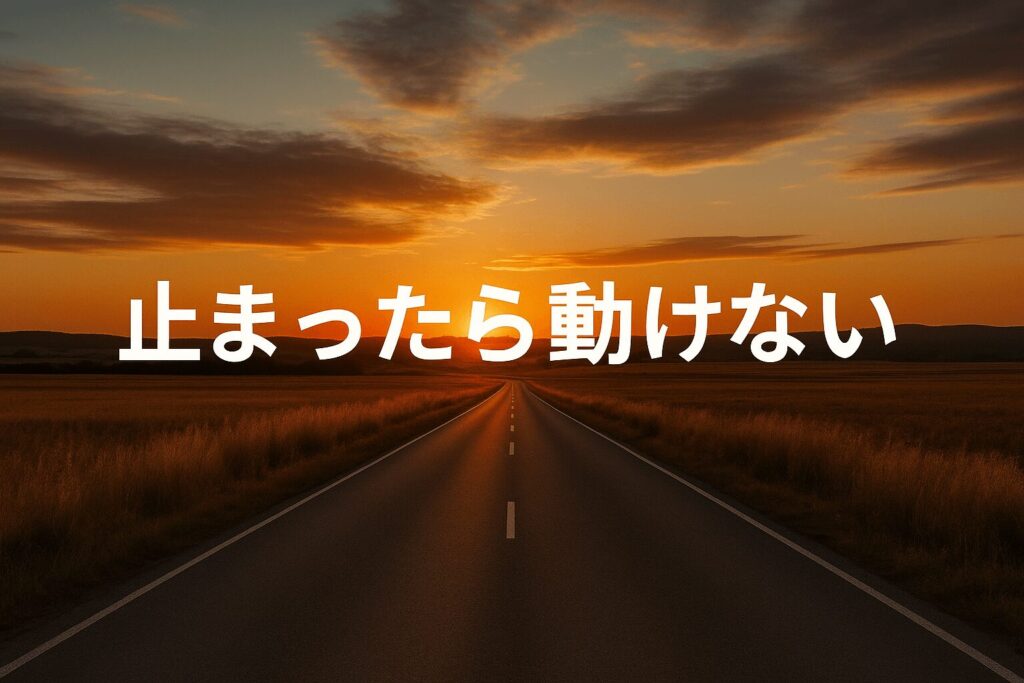
ずっと前から気になっていたことがあります。
何かしようとして途中で中断したり、休まなければならない時間が発生した場合、「再開が難しくなる問題」です。
単純にさっきやっていたことの続きをすればいいだけなのですが、拒絶反応が出てしまいます。
やる気スイッチが上手く戻らない。
少し前の思考の行動していた状態になかなか入れない。
そして中断してる間に、違うことが頭に入り込んできて、そっちに気持ちが持っていかれてしまう。
気づいたら知恵袋を見てたり、youtubeを見たり、別のことを考えてたりして、なにしてたんだっけ?というようになります。
良くあるのが、chatgptに質問して、回答が返ってくる数秒~数十秒の待ち時間。
この少しの時間だけでも、待つという状態が何故か苦手すぎるのです。
何かしらの刺激が欲しい。
でも、昔はずっと無の状態で耐えていたのが普通だったはず。
何故、今になってこんな状態になってしまったのだろう。
引きこもった影響で、ADHDの要素が表面化して出てきたのだろうか。
発達障害は後天的に発症するものではないので、元からADHDの一部の潜在が眠っていたのかもしれない。
発達障害だから「脳の切り替えが苦手」というのはADHDでよく聞く話です。
私はASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けています。
しかし当時発達障害の検査では、ADHDでは無いと言われていました。
でも、このような途中で止まったものに戻れない感覚というのは、よくADHDの特徴としてあげられます。
なので、ASDだけどADHDの特徴も一部かじっているのかもしれない。
この切り替えの苦手感はADHDの特徴ですが、ASDにもあります。
ASDは、ひとつの流れやパターンに沿って物事を処理するのが得意だと言われています。
でもその流れが中断されると、再び同じテンポや状態に戻るのがすごく難しい。
さっきの状態に復帰するという操作が、ものすごく重く感じる。
パソコンのスリープ復帰がめちゃくちゃ遅いみたいな感じです。
さらに、待ち時間のように目的がぼやけている時間も苦手です。
ただ待っているだけの状態だと、頭が落ち着かず、次に何が来るかわからないとか、どれくらい待つのかわからないという微妙な曖昧さに不安や不快感があります。
そうなると、普段している安心できる刺激や行動に逃げたくなる。
だから気づいたら、無意識にYouTubeや知恵袋を開いてしまう。
やる気がないのではなくて、脳の構造上そこに戻れないだけなのです。
ADHDの待ち時間で気が散ってしまい、戻れなくなる特徴もASDと似ているかもしれません。
ADHDの人は、刺激を求める脳が待ち時間に耐えられず、つい別のことに意識が飛んでしまう。
ASDの場合は、一貫性の継続の流れや不確実さに対して強いストレスを感じやすく、それによって思考や行動の再起動が難しくなる。
原因は違っても、途中で脱線して戻れないという結果的には同じです。
どちらのタイプにしても、途中で何かが止まることに脳がとても弱いです。
そして一度止まってしまったものを、再び動かすには、ものすごく大きなエネルギー(決意)と準備(心持ち)が必要になってしまうのです。
脳の切り替えが難しいとはどういうこと?
うまく説明できるかわからないけれど、自分なりに書いてみます。
たとえば、ひとつのことをしてる時に、何かの理由で途中で止まらなきゃいけなくなるとします。
で、またそれを再開しようとすると…何故かすごくしんどくなります。
体じゃなくて、頭の中が無理という拒絶反応。
例えるなら、心に50kgの重しを付けられた感じです。
「前のことの続きするだけでしょ?」と言われるかもしれないですが、自分の中では、前と同じ気持ちとか、考えてたことに戻るのがすごく難しくなり、なんか、うまくスイッチが入らないというか…。
前の自分とは別の人になったみたいな感覚のときもあります。
頭の中が、違うことでいっぱいになって、もう戻らなくていいや状態になる事もあるし、何やってたんだっけ?って忘れちゃう時も。
ゲームとかパソコンみたいに、セーブしてたところからすぐ始められたら楽なのですが。
でも、実際は自分の脳はなかなかロードしてくれない感じで、しかも途中でフリーズしたりする。
ASDの人あるあるなのかもしれないです。
ADHDとASDに共通する中断に弱い特徴
ADHD、ASDのどちらも、途中で止まるということにすごく弱いところがあります。
でも、その理由はちょっと違う感じがします。
ADHDの人は、よく刺激を求めてると言われます。
だから、待ち時間とか、何も起こらない時間がすごくつまらなくて、すぐ別のことに気がいってしまう。
少しでも退屈を感じると、他のことを探し始めて、それで元のことに戻れなくなる。
逆にASDの人は、いつも通りがすごく大事で、ひとつの流れの中で安心してるところがあります。
でも、その流れが途中で止まると、もう一度そこに戻るのがかなり難しい。
同じようにやろうとしても、気持ちとかテンポがずれてて、前みたいにできなくなったりします。
ようするに、ADHDは次の刺激に行っちゃう、ASDの場合は元の流れに戻れない感じです。
理由は違うけど、どっちも「途中で止まると困る」っていうのは同じです。
この途中から再開するエネルギーはかなりの莫大な決意や意思が必要になります。
特にやりたくないことをやっている時などは。
なぜ今、切り替えがより苦手になったのか
数年前からちょっと感じていたのですが、「切り替えができない」がどんどん強くなってきている気がします。
なんでだろう?と考えてみるとやはり、末期的な引きこもりが関係しているのではないかと思われます。
普通の人の場合、外に出たり、人と会ったりしてると、切り替えをしないといけない場面が多いです。
でも、引きこもってずっと家にいると、そういう場面がないので、ぜんぶ自分のペースで行ってしまう。
PCに座っているのも、ごろごろするのも、youtubeや知恵袋を見るのも自分の気の向くままに。
そんな生活を23年以上続けてきた影響かもしれない。
でも、悪化したというよりは、もともとADHDの隠れてたものがはっきり出てきた、という感じかもしれないです。
真性ひきこもりだと、自分の脳のクセや苦手なところが前よりもより際立つようになってしまった。
そもそも母親も物を捨てられずゴミ屋敷でADHDっぽいところもあったので、それが私の中に隠れていた脳の何かが発現してしまったのかもしれない。
だから脳の切り替えが出来ないのは、サボっているとかではなく、ちゃんと理由があることだ、と言い訳したいところです。
まとめ
自分はASDの診断を受けていますが、ADHDではないと言われていました。
しかし最近は「これ、ADHDの特徴に近くない?」と思うことが増えてきました。
特に、途中で何かを中断すると再開がすごく難しいこと。
注意力散漫な点も。
これはADHDにもASDにもよくある特徴で、どっちでも「脳の切り替え」が苦手という共通点があります。
ADHDは刺激を求めて気がそれやすい。
ASDは流れが止まると復帰がむずかしい。
理由は違うけど、結果的に戻れないという困りごとは似ています。
しかも、長年引きこもりの生活をしてきたことで、その切り替えのしにくさがどんどん強くなってきた気がします。
環境のせいもあるし、もともと持っていた性質が今ごろになって表に出てきた。
そもそも、発達障害の人は、ASDもADHDも両方併発していることがよくあるそうです。
同じような症状の人はいないけれど、ASDで一部のADHD要素をかじっていたり、逆も然り。
人生が崩壊しているので今更どうでもいいことなのですが、発達障害は本当に生き辛いハンデだと実感しています。
