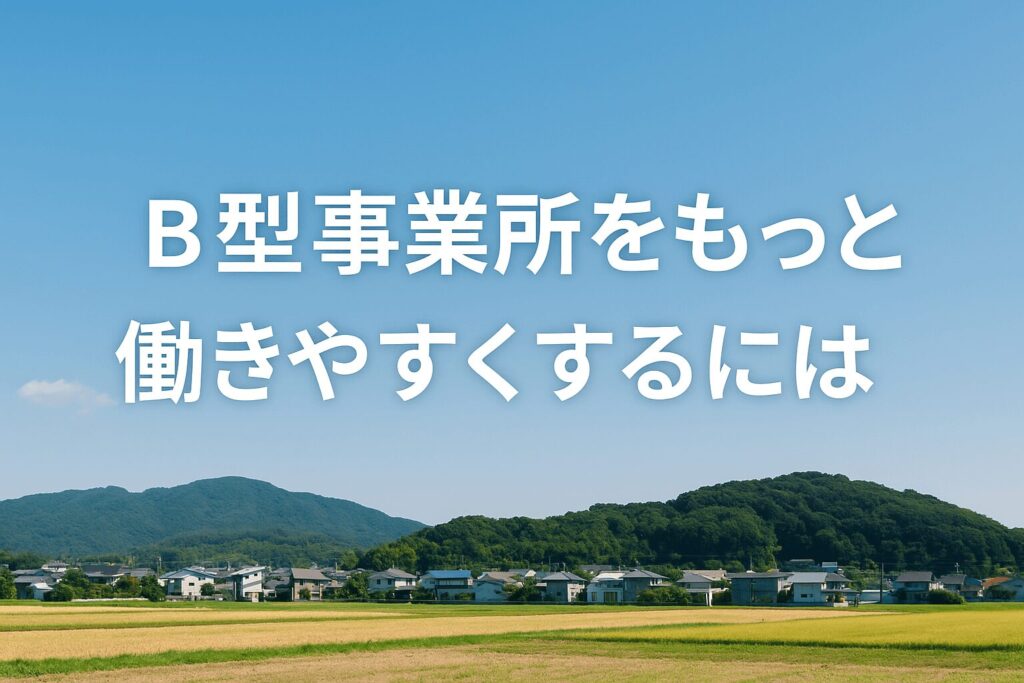
障害や病気などで一般就労が難しい人が働く(働くことに慣れる練習をする)ことが出来るB型事業所。
最近は、B型事業所で働くのも一つの選択肢かもしれない、と考えるようになりました。
AIで収入を得ようと挑戦してきましたが、思うように結果が出ていないからです。
といっても、B型事業所は時給が200円前後なので、はっきり言ってお金目当てで働くのは馬鹿らしいです。
そもそもB型事業所は、A型事業所で働けない人や、仕事の前段階の慣れや、対人関係の経験を積む場です。
でも、さすがに200円はおかしいと思います。
B型事業所の仕事内容的に、生産性が低く稼げないので仕方がないようです。
しかし、そこは国が補助金を出して最低賃金くらいにすべきです。
B型事業所で働く人はそれほど多く無い(約30〜35万人程度)ですし、他の無駄な他の補助金を出すくらいなら福祉に回してほしい。
日本は本当に障害者やそっち系の支援や理解が不当に低いと思う。
B型事業所の平均工賃は月額1万6千円前後。
欧米の障害者雇用支援プログラムでは数万円〜数十万円の水準が一般的だそうです。
日本の福祉分野への予算配分は先進国の中でも低めで、高齢者福祉(介護)に比べて障害者福祉は二の次にされています。
B型事業所でフルタイム並みに働いたとしても、月収は1〜2万円程度。
これでは絶対に生活は出来ないです。
ということで、B型事業所をどうすればもっと待遇が良くすることが出来るのか考えてみたいと思います。
B型事業所のメリット・デメリット
B型事業所のメリットは何だろう。
普通に働いても、得られるのはお小遣い程度で、正直ほとんど意味がない。
個人的には、働いていると実感できるくらいなのではないかと思っています。
一応、社会人として活動しているという自負。
他の人との交流が出来るので少しは自己肯定感が上がるはず・・。
私のように真性ひきこもりにとっては、社会復帰の第一歩のトレーニングくらいにはなるかもしれない。
後は、昼夜逆転の生活や生活リズムを掴めるなど。
B型事業所で働くということは、変な言動をしても差別や偏見の目で見られないと思うので、気負わず仕事に取り組めるかもしれない。
デメリットとしては、やはり工賃が時給換算で200円前後、月に1〜2万円程度しか得られないことです。
正直、わざわざ外に出てメンタル改善や働く練習のために200円程度で時間を費やすことが勿体ない、意味が無いと思ってしまいます。
時間は有限であることを考えると、B型事業所の現状の意義には疑問を感じざるを得ないのです。
もし、時給が最低賃金を保証してくれるのであれば、全く別なのですが。
ただそのためにはやはり、作業に生産性を求められてしまうのです。
だから、そこは国が絶対支援すべき法制度をするべきです。
現行ではあまりにも酷いと思う。
この時給200円前後は、2000年代半ばからずっと続いていて、大きな改善はされていないようです。
今の物価高を考えると、もはやお小遣い以下と言ってもいいと思う。
B型事業所を改善するには
そもそもB型事業所は福祉サービスですが、労働も兼ね備えているのが問題だと思う。
法的には雇用ではなく、就労機会の提供や社会参加の促進が目的で、収入は本来の目的ではないのです。
でも作業をしている以上、働いているという感覚があるだろうし、責任も発生するのに、報酬だけは訓練のお礼みたいな扱いになっています。
これを改善することがマストだと思う。
ということで、国がすべきことは工賃補填制度の見直し・強化です。
でも、今の制度では不可能です。
調べてみると、B型事業所の利用者が作業したことに対する対価(工賃)は、その仕事の収益からしか支払われないようです。
ようするに、利用者の作業の生産性が限りなく0であれば、給料も0ということです。
B型事業所は国の補助金で運営されていると思っていたのですが、A型事業所のように最低賃金保障があるわけではなかったのです。
ちなみにB型の国の補助金は、職員の人件費や施設の運営費 に充てられるのが原則だそうです。
A型事業所も労働者自身が最低賃金を払えるだけの生産性(売上)を求められますが、B型事業所は雇用契約はないものの、実態としては低い工賃に見合う作業を担わされているのです。
B型事業所に最低賃金を課してしまうと、利用者自身の生産性もかなり求められてしまう為、能力的に難しいのだと思います。
B型事業所を最低賃金にするには
B型事業所の利用者が人並みの賃金を得るためには、事業所の売り上げを上げる作業量が必要になります。
しかし、利用者にそのような負担は難しいですし、本来の目的である社会参加やリハビリ的要素を失ってしまいます。
でも私自身もA型はちょっと難易度が高い、B型は賃金が安すぎて時間の無駄だと感じている人も多いと思います。
そこで、B型事業所でも最低賃金を得られるようにするには、どうしたらいいのでしょうか。
国による直接補填制度の導入
利用者が働いた時間に応じて、工賃と最低賃金との差額を国や自治体が補填する仕組みを導入する。
これによって「作業は福祉として柔軟に」「収入は生活支援として安定的に」という役割分担が可能になるのです。
多様な就労モデルの開発
農業や軽作業だけでなく、ITサポート、データ入力、AIの補助タスクなど、新しい形の就労機会を取り入れる。
生産性の幅を広げることで、補填に頼らずとも一定の工賃向上が期待できる。
障害者福祉への予算を増やす
現在、日本の社会保障費は高齢者福祉(介護)に偏っており、障害者福祉は後回しにされてしまっています。
では何故、障害者に厳しいのでしょうか。
理由として、日本の政策文化には社会が全員を支えるという発想よりも自分で何とかするのが基本という自己責任の思想が強く残っているからです。
障害者に対する支援も国が十分に保障するより、家族や地域に任せるべき、という考えが根強いため、予算の優先度が低く抑えられてしまっているのです。
あとは、現政権がほぼ高齢者にしか支持されておらず、その票目的で社会保障費の大部分が年金・医療・介護といった高齢者向けに沢山導入されているとみています。
財源問題
そもそも日本は財政赤字が酷く、障害者福祉や若者支援の予算が後回しにされているようです。
就職氷河期世代に対しても、ほぼ何も支援していないですし。
弱者に対して本当に厳しい国だと思う。
個人的に、ほぼ全く成果を上げていない少子化対策庁(こども家庭庁)とかいらないと思っています。
こども家庭庁の予算総額は、令和7年度案で約 7.3兆円 といわれています。
保育・子育て支援、児童手当、児童相談所運営など様々な事業に割り当てられているようですが、もう何十年も少子化が解決していないし、減り続けています。
実際にB型事業所の利用者は30〜35万人と言われています。
平均月80時間ほど働いていると計算して、最低賃金で換算すると2兆円規模の補填が必要になります。
でも、全員が週5日・4時間通っているわけではないですし、参加時間は人によって全く違います。
なので、実際の必要予算はこれより低く、0.2〜0.3兆円規模に収まるはず。
また、そこまでしなくても、もっとB型事業所の作業内容に対する生産性を上げたり、何かしらの改善すればもっと費用対効果は良いと思うのです。
まとめ
今回は、B型事業所のことについて、いろいろ考えてみました。
正直、時給200円前後って…もう無いのと同じくらいのレベルだと思います。
ちょっとした作業とか、生活リズムを整えたり、人と少し話したりするためなら、別の制度としてやった方がいいんじゃないかなと思います。
それよりも、最低賃金くらいはちゃんと得られる新しい制度を作ってほしいです。
A型みたいにきっちり働くのは難しいけど、B型だとほぼボランティア扱いみたいで意味がない。
その中間くらいの「福祉的な働き方ができる中間就労の場所」があってもいいと思いました。
また、B型事業所レベルの人のための会社での雇用みたいな仕組みがあってもいいと思います。
今は一応障害者雇用という枠がありますが、それだと一般的な仕事が前提になっていて、負担が大きすぎる人もいます。
だから、そのもう一つ下の段階のB型レベルの障害者雇用枠みたいなのがあってもいいと思うのです。
そして、私みたいに外に出るのが難しい人のために、家から参加できるリモート福祉作業所みたいなものがあると助かります。
通えないから何もできないっていうのは、やっぱり悲しいです。
あと、ちゃんと作業してるなら、それなりの工賃はあっていいと思います。
今は福祉っていう名前でごまかされてる感じがあります。
国はもっとB型事業所に関わってる人たちのことをちゃんと見て、働きたいけど難しい人でも安心して働けるようにしてほしいです。
